2014年10月23日
茅葺き屋根に学ぶ。

こんにちは。紅葉前線は戸隠の山々を下り、標高1200メートル(中社周辺)前後での紅葉が見頃になっています。
久しぶりに好天に恵まれた先週末は、多くのお客さまがピークを迎えた鏡池の紅葉を楽しみにいらっしゃいました

さて、今回はそんな戸隠で現在進行中、茅葺き屋根の修復・葺き替え工事のレポートです。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、平成25年4月より国の歴史まちづくり法に基づく「長野市歴史的風致維持向上計画」において、戸隠中社・宝光社地区が、歴史的風致地区に指定されました。
そして、戸隠の歴史的景観において重要な旧宿坊旅館の茅葺き屋根の整備がこの夏から地区内3ヶ所で行われています。
以前のブログに、宝光社の武井旅館が登場しましたが、今回はその斜向いにある越志旅館の工事の様子を取材させていただきました。
工事前の越志旅館の写真はこちらの記事に。
築250年以上の主屋。約60年ぶりの葺き替えとなる今季は南側(上の写真;左の植木に隠れている部分)で工事が行われています。

私もヘルメットをかぶり、足場を上って工事の様子を見学させていただきました。
茅葺き職人さんは、株式会社小谷屋根の三代目・松澤朋典さん。
11年目ということで、意外にも若く驚きましたが、お祖父さまの代から伝わる技術をしっかりと引き継ぎ、この現場は主におひとりで施工されています。
松澤さんが持っているのが、葺き替える茅の束。長さは約2m、500〜600本の茅が1束になっています。

越志旅館の葺き替え工事は3年計画で行われ、今季の工事では3,600束ほどの茅を使うそうです。
松澤さんいわく、戸隠の茅葺き屋根の特徴として、短い茅を使って継ぎ足し修繕しながら維持してきた歴史があるそうです。
また、茅の葺き替えには大変な労力と費用が必要で、茅場の維持管理を地域で行っていく必要があるのですが、その文化は時代の流れとともに途絶えつつあり、戦後安価に手に入る麦わら等を混入して修繕するようになったということ。
そうなると、茅同士の力が伝わり合わず、傷みやすいそうです。
雨垂れによって茅が濡れ、虫が発生すると、鳥が虫を食べにきてフンを落とし、微生物の分解がおこり、植物が生える...こうなると、屋根はどんどん傷んでしまいます。
実際、今回の修理で古い茅を剥がしていくと、骨組みの柱も傷んでいることがわかり、新しい柱で組み直したということです。
今回使う茅は、従来使われていたものよりだいぶ長く、その分、茅同士が力を伝え合って屋根を支えるため、丈夫で長持ち。
出雲の遷宮と同じで、60年(一代)は必ずもつということです。
「茅葺きは、最高にエコなんです」と松澤さんは言います。
その訳は、60年経っても使える部分は枕材として次の葺き替えに用い、使えなくなった部分は有機肥料として畑に入れ、おいしい有機野菜に生まれ変わる。
そのおいしい野菜を食べて、家族が健康に暮らし、また次世代につながっていくという循環の資材であるということ。
今回剥がした短い茅(上写真の足場の上に並んでいるもの)も、茅を傾斜させる際の枕材として再利用しています。
新たに葺かれた茅は、小谷村から運んできたもの。
小谷村の牧の入地区には、古くから地域の建築資材としての茅を育んできた茅場があり、地域が一帯となって茅場を維持管理する文化が受け継がれてきたのだそうです。その営みが評価され、今年、文化庁の「ふるさと文化財の森」として認定されたということです。

写真:小谷村牧の入地区の茅場(松澤朋典さん提供)
小谷村でも、現在は茅葺きの民家は少なくなり、今回のように、北信地区の文化財級の建物の屋根資材として使われることが多いそうです。
景観を守るために、茅葺き屋根を守るということはすなわち、文化を守るということ。
文化を残したいという地域の人々の強い意思と努力、つながり。戸隠には失われつつある大事なものが小谷村にはありそうです。
茅の厚みはおよそ90cm。
ただ闇雲に茅を積み重ねていくのではなく、最初に建物の形をよく見て分析し、イメージ(設計図)を描くそうです。そして、葺き具合を調整しながら作業を進めます。
茅を手に持ち、みるみるうちに、屋根として葺いていく松澤さん。
その手の早さに、圧倒されました

今月末には茅葺きの工程が終わって足場を外し、鋏を使って仕上げの工程が行われる予定とのこと。
今季の工事が竣工する頃、戸隠に初雪が降るでしょうか。
美しく生まれ変わった屋根を見るのが楽しみです。
続きを読む
2014年10月10日
歩きながら伝える戸隠の秋の魅力
こんにちは。半月近く更新をさぼってしまいました。この間、樹々の紅葉が進み、刈り取られた稲がはぜ掛けされ、秋そばの刈り入れも始まった戸隠です。
先週に引き続き、今週末も大型台風が接近する予報ということ。
先日(10月8日)の皆既月食を見ながら、「やはり今年は自然が我々人間に何かを知らせてくれる年なのだろうか」などと考えました。
改めて、先月末の御嶽山の噴火で犠牲になった方々のご冥福をお祈りするとともに、一刻も早く、行方不明者が発見されるようにと祈るばかりです。
さて、冒頭から少々重い話になりましたが、気分を変えて、今日はラジオ番組のお話です。
北陸新幹線の長野ー金沢間開業に向けた長野県の広報番組「GO! GO!信州」に戸隠をご紹介いただけるということで、僭越ながら私が戸隠観光協会を代表してインタビューを受けました。
ラジオの収録は初めてで、少々緊張しましたが、インタビュアーの辻深雪さんと戸隠神社奥社参道を歩きながら雑談形式でいろいろお話してきました。
久しぶりに歩く奥社参道は色付いた樹々に木漏れ日が当たる感じがとても美しく、落ち葉を踏みしめる音にも秋の深まりを感じました。

辻さんは妙高市出身ながら奥社を訪れるのは初めてということで、随神門や杉並木の景色にとても感動していらっしゃいました。
今や名物と化した吉永小百合さんCMで登場した杉の木のウロにも大興奮!
人前でしゃべるのが不得意な私ですが、精一杯奥社参道の魅力、今月25日から始まる戸隠そば祭りのPRをさせていただきました。
放送は24日(金)だそうです。よろしければ聴いてみてくださいね

.................................................................................................................
長野県はSBCラジオ
「情報わんさか GO!GO!ワイド らじ☆カン」内14:20~およそ8分
富山県はKNBラジオ「でるラジ」内 12:50~
石川県はMROラジオ「げつきんワイド おいね☆どいね」内 9:50~
.................................................................................................................
おまけ。
慣れないラジオ収録のあとは、少しだけ自分へのご褒美を、ということで、戸隠森林植物園を覗いてきました。
真っ赤に染まる前のグラデーションが素敵なモミジ
マユミの実
シオデの実
そして、大好きなカツラの紅葉。
甘い匂いをそのまま懐に入れて持って帰りたい衝動にかられました。
人影はほとんどなく、ひっそりと秋が深まる植物園内は、得も言われぬ色彩の宝庫。
鏡池も素敵ですが、静かに秋を感じたい方に、おすすめします!
2014年09月09日
戸隠旬ウォークレポート4・戸隠古道一之鳥居〜宝光社
こんにちは。昨夜は中秋の名月でしたね。戸隠ではよく晴れて、月灯りの下でお団子をいただくことができました

ただ、朝晩ぐんと気温が下がるようになりましたので、お出かけの際の服装にはどうぞお気をつけください(という私も風邪をひきました
 )
)さて、今回は9月5日(金)に行われた「第4回戸隠旬ウォーク」のご報告です。
当日は小雨模様でしたが、お申込いただいた21名の皆さま全員が、一之鳥居苑地駐車場に集合しました!
ガイドは戸隠小舎のご主人でプロスキーヤーの佐々木常念さんと、戸隠牧場で引き馬などもしている村田幸恵さん。
お二人とも戸隠生まれ、戸隠育ちの、ベテランガイドさんです。
準備体操の後、集合写真を撮って、元気に出発です!
人数が多いので、2チームに分かれて歩きます。
私は村田さんチームにお邪魔しました。
一之鳥居苑地からカラマツとアカマツ林を抜け、約5分で戸隠神社一之鳥居跡へ。
戸隠神社の元神領(千石)の入口として、18世紀末に大規模な石の鳥居が建造されましたが、弘化4年(1847)の「善光寺地震」で倒れ、今はその一部が残っています。
その後、明治時代に、奥社から運んだ大木で木造の鳥居が建てられましたが、老朽化して昭和60年(1985)に取り壊されたそうです。
鳥居建設の奉行を努めた中社の極意家(宿坊極意)には大木を乗せて曳いた大ぞりが残り、石の鳥居柱の一部も残っていると、ガイドさんから詳しい説明がありました。
また、この場所には『戸隠古道拓本集印帳』の最初のポイントがあり、拓本をとる参加者もいました。

今回、地元から参加してくださったフランススキー学校の小林校長先生からは、
「おれがこどもの頃にはこの辺に売店が立ってた」という貴重なエピソードもきかれ、往時に思いを馳せることができました。
一之鳥居付近は、最近数少なくなったマツムシソウの群生地でもあります。
神領に入ったとたん、ぽつぽつと雨に出迎えられたご一行。傘をさしながら古道を歩きます。
一之鳥居から奥社までの道標となる丁石(ちょういし)の、はじめの「一丁」。
ちなみに、一丁(町)は約109メートル。宝光社までが43丁(4.7km)、中社までは53丁(5.8km)、中社から奥社までが36丁(4km)です。
一之鳥居から七丁で大久保に到着。
大久保の茶屋の裏山に咲いているこのお花は、フシグロセンノウ。ビビットカラーなので、一見園芸種のように見えますが、在来の山野草だということを、ガイドさんの説明で初めて知りました。
ここは善光寺からの戸隠表参道と、柏原(信濃町)からの戸隠下道が合流する交通の要所。江戸時代にも二軒の茶屋がありましたが、当時は蕎麦ではなく、「力餅」が名物だったそうです。
「こちらへどうぞ」とガイドさんが案内してくれたのは、大久保西の茶屋の主屋の背後にある岩屋。
岩と岩の間に「龍のしっぽ」と呼ばれる穴があり、一説によると戸隠山の九頭龍権現がこの穴を出入りしていたということ。
「岩戸里宮」として、九頭龍権現を祀っているそうです。
私有地なので、参拝される方は、大久保西の茶屋さんに一声かけてお入りください。
九頭龍権現様にご挨拶したところで、効果覿面!?雨がザーザー降ってきました

晴れていれば野鳥や虫の声が聞こえ、山野草も楽しみな遊歩道ですが、傘をさしながら早足で進みました。
祓沢のそば展望苑に到着。
戸隠連峰は霧にかすんでいましたが、一面に広がるそば畑を初めて見たという方は、
「晴れたときにまた来たい」といいながら写真を撮っていました。
祓沢にはその名のとおり、戸隠信仰の修験者達が禊ぎをしたといわれる沢があります。中院道と宝光院道の分岐点を示す道標がありますが、上部には大きくえぐられた跡が。明治の廃仏毀釈で梵字が削られたということです。

「左宝光(院)御宮迄十二丁
徒夫中(院)御宮江通ぬけ」( )は削られています。

祓沢から先は石畳が敷かれ、戸隠の古き佳き時代の面影が残る古道です。
雨脚が強いので、もうひとつのビューポイント・湯之嶺夕陽展望苑はパス。晴れていれば戸隠連峰と北アルプスのパノラマを展望できるので、ぜひまた歩いてみてくださいね。
森の中の道を抜け、舗装路との合流点の先に「熊の石塔」が現れました。
大きな石を組み合わせた五輪塔。熊野信仰の跡だと伝えられています。
熊野古道を歩いたことがあるという参加者の方の話を興味深くききながら、宝光社を目指します。

ひとりでは心細いような鬱蒼とした杉木立の道ですが、「皆で歩けばこわくない」!
ギンリョウソウ(銀嶺草)が見事な白い顔を出していました。
雨にも負けず、いろいろな話をしてくれるガイドさん。
こちらの白樺の幹が黒くなっているのは....?
信州では「カンバ」でお盆の迎え火を焚きますが、戸隠では白樺の樹皮を使います。
白樺の樹皮は一度剥がすと再生せずに黒く残ります。幹が黒くなっている白樺があれば、そこは人が入った山という印だということです。
お昼を少し過ぎた頃、戸隠神社宝光社の鳥居に到着!
コケや緑が雨に濡れて一層濃く見え、晴れの日とは違った趣でした。
274段あるという石段をゆっくり上っての宝光社参拝は、なんだかとてもご利益がありそうです。

ガイドさんから来年は戸隠神社の式年大祭で、この宝光社の御祭神が御神輿に乗って渡御し、中社の御祭神とご対面するという説明がありました。
「渡御の儀」は平成27年の5月6日。楽しみですね!
参拝を終えて、お腹も空いてきた頃、武井旅館に到着。
雨の中の散策、皆さまお疲れさまでした!
築約300年の宿坊のお座敷でいただく女将さん特製の手打そば。
旬野菜の天麩羅や、煮物もとてもおいしく、雨に濡れた体が一気に癒されました

その後、女将さんから家宝の秘仏のお話、茅葺き屋根の葺き替えのお話など、ここでしか聴けない興味深いお話も伺うことができました。
現在、歴史まちづくり法の町並み整備事業が行われている戸隠宝光社・中社地区。
今年、長野市の景観風致建築物にも指定された武井旅館では、茅葺き屋根の葺き替え工事の真っ最中。
お隣、鬼無里と信濃町からの熟練の茅葺き職人の方が来て、7月から工事が始まり、今秋は西側の屋根を葺き替えるそうです。

こちらは、武井家の新たなお宝。
戸隠山の稜線等に咲く希少な高山植物「羽蝶蘭」で、宝光社には咲くはずのないこの花が、なんと、古い屋根の上に咲いていたそうです。
女将さんは、風に運ばれて根付いた貴重な一株を大事に育てたいとおっしゃっていました。
九頭龍権現様の歓待にあった今回のウォーキング。皮肉なことに食事が終わった頃には雨が上がりました

次回の戸隠旬ウォークは10月24日(金)。鬼女紅葉伝説が伝わる柵地区荒倉山塊を歩きます。乞う晴天!
2014年09月03日
戸隠秋花図鑑(2)
こんにちは。「涼しくなったね〜」「あっという間に夏が終わって」そんな会話が飛び交う秋のはじめ。
峰の上に雲が立ち、黄金色の稲穂が揺れ、とんぼが舞う戸隠の秋が、私は大好きです。
秋花図鑑第二弾は、バードライン沿い、「そば展望苑」から。
いわずと知れた戸隠連峰のビュースポット。8月中旬から咲き始めたそばの花は、今まさに満開。
間もなく実となり、10月末からの戸隠そば祭りの頃には、おいしいお蕎麦となって再び私たちを喜ばせてくれるでしょう。
お次は戸隠スキー場(越水ゲレンデ)へ。
第2リフトの下の斜面は、一見すると草ぼうぼう...ですが、変に人の手が入っていないのが素晴らしいところ。
少し歩くだけで、多種多様な草花と出会うことができます。

ツリガネニンジン/キキョウ科
アキノキリンソウ/キク科

オヤマリンドウ/リンドウ科
ユウガギク(キク科)とガマ(ガマ科)
奥の方には昔から戸隠の貴重な建築資材となってきた茅(ススキ)の茅場があります。
スキー場の茅場で昨年刈った茅を一部利用して、現在宝光社地区の宿坊旅館で葺き替え工事が行われています。
その様子は次回以降で詳しくお知らせしますね。
スキー場を後にし、高妻通りから戸隠キャンプ場方面へ。緑が少しずつ黄色っぽくなってきました。
キャンプ場の入口付近では、風に遊ぶトンビの声が聴こえました。
キンミズヒキ/バラ科
ノコギリソウ/キク科
ゲンノショウコ/フウロソウ科
締めくくりは、奥社参道・戸隠森林植物園へ。
この花を見ずに秋は迎えられません。
オオシラヒゲソウ/ユキノシタ科
夏の間、あれだけ賑やかだった野鳥たちは、もうどこかへ渡ってしまったのか、森の中はとても静か。
小川のせせらぎの音が、いつも以上に心地よく耳に響きます。
ヤマトリカブト/キンポウゲ科
いつ来ても、そのまま額に入れて持って帰りたいような自然の造形美にあふれている森林植物園。
フラワーアレンジメントをお勉強中の方は、一度、植物園の遊歩道を歩いてみてはいかがでしょうか

オオバセンキュウ(セリ科)とキツリフネ(ツリフネソウ科)
ツルニンジン/キキョウ科
サラシナショウマ(キンポウゲ科)
2014年08月18日
戸隠秋花図鑑

こんにちは。しっとり梅雨のような天候が続いたお盆休みが終わりました。例年お盆を過ぎるとぐっと涼しくなる戸隠ですが、今年は既に立秋(8月7日)とともに秋の気配を感じました。
夜になればコオロギ、スズムシ、キリギリス...コンビニも、居酒屋もない山ですが、エアコンをかけず、虫たちの大合音を聞きながら布団にもぐる暮らしを経験してしまうと、もう都会暮らしはできないなと思う今日この頃です。
さてさて、秋といえばのお花を見たくて、観光案内所の開所前に、戸隠森林植物園に立寄り、みどりが池の周囲を歩いて来ました。
夏休み中は、朝早くから車の交通量が多いですが、9時前の植物園はとても静か。草花に蝶やとんぼが止まるのを眺めていると、時が経つのを忘れてしまいそうです。
こちらは、タチアザミ(キク科)with タテハチョウの仲間たち(中央はクロアゲハ)。
八十二森のまなびやの向かい側の花壇には、期待通り、マツムシソウ(マツムシソウ科)が咲いていました
 with トンボ(詳細不明)。
with トンボ(詳細不明)。
まだ咲き始め。例年並みだと9月初め頃まで可憐な花を咲かせそうです。
トップ写真にも載せましたが、この時期、一番といってもいいほど目を引く光景が、ヨツバヒヨドリwith アサギマダラ。
海を渡るチョウとして脚光を浴びているアサギマダラ。この美しい浅葱色の羽根の下に、驚異的なエネルギーを秘めているのかと、見とれてしまいます。
昆虫と植物だけでなく、植物同士のコラボレーションにも注目。
ブナ科の樹に絡むツルアジサイ(ユキノシタ科)。右下の赤はケナシヤブデマリの実。

地味だけれど、よく見るとかわいいノブキ(キク科)。

池の周りを賑やかすのは、シラネセンキュウ(セリ科)。
たとえ日常の合間の短時間でも、自然の中に入る時間は、本当に心が洗われ、癒されるひとときです。
涼しくなって、花を愛でながらの散策にはもってこいの季節。
夏の疲れを癒しに、ぜひお出かけください。
2014年07月29日
戸隠旬ウォークレポート3・不動尊磨崖仏&鏡池

暑中お見舞い申し上げます。先週末は戸隠でも猛暑となりましたが、その後一気にクールダウン。おかげさまで布団をかけてぐっすり眠れます。
さて、今回は7月25日(金)に行われた第3回戸隠旬ウォーク「鏡池と不動尊磨崖仏をめぐる涼感ウォーキング」のご報告です。

この日のガイドは戸隠登山ガイド組合の組合長・ペンションピオレの吉本照久さん。
集まったお客さまは県内外から17名!戸隠森林植物園森のまなびや前で軽く準備体操を行い、出発です。

7月終わりの植物園では今が盛りと草木が生い茂り、薄暗い場所もありますが、ニワトコの赤い実や、ヨツバヒヨドリ、シモツケソウやノカンボクなどが見られます。
立ち止まって見ればこんな可憐な花も...シキンカラマツ(写りが悪くてスミマセン)。
ベテランガイドの吉本さん。雪深い北信地域ならではのあがりこ型の樹の説明もとてもわかりやすいです


冬に樹を切る意味は、(樹の水分が少ないだけでなく)雪上だと運び出すのに好都合だという説明に納得!
植物園内を20分程歩いて鏡池の入口の天命稲荷まで来ました。
天命稲荷は戸隠最後の修験者といわれる姫野公明女師(1898ー1970)が建てたお宮。公明師は稀に見る霊媒能力の持ち主で、戸隠山で数々の修業をされ、越水に公明院を構えられました。霊告により戸隠山三十三窟のうち三十一窟(九頭龍社・奥社を除く)を探し出して復興(岩壁のわずかな窪みに石祠を奉納)したのが、最大の事績といわれています。この天命稲荷があった場所も、霊告により見つかった1200年前の人塚ということで、天命により豊受大神を祀ったことが名前の由来だそうです。ちなみに、3月の春分と9月の秋分の彼岸には、日の出が飯縄山・怪無山・天命稲荷を一直線に結ぶそうです。
そんなスピリチュアルスポットを後に、鏡池の外周から不動尊を目指します。

歩き始めて30分、鏡池との分岐点「不動尊まで60分」の道標に到着。水分補給をした後、少し急な山道を登っていきます。
広葉樹と針葉樹(杉)が混在する山道を15分程登ったところでピークに到達。木造の古い小屋(遥拝小屋)でひと休み。
こんどは谷を下ります。しばらく行くと、右手に少し開けた空間が現れました。
この辺りは約500年前、真言宗系のお寺(西光寺)があった場所。西光寺は主に西岳を中心に修業をしていた山伏の拠点で、
その後、真言宗と天台系の顕光寺(現在の奥社、中社、宝光社)の間に激しい争いがあり、西光寺は焼滅・亡滅したそうです。
そんな歴史に思いを馳せた後は、不動沢(不動尊が立つ沢)へ向け最後の下りに突入です。
左側は崖なので、よく気をつけて手足を使い、ゆっくりと下っていくと、沢の向こうに不動尊が見えて来ます(トップ写真)。
不動沢沿いの断崖絶壁・頭上4メートルぐらいの岩に彫られたお不動様。想像していたよりは小さく感じましたが、こんな高いところに、どうやって彫像したのか、想像すると奇跡のような仏像です。正確な作者も不詳ですが、江戸時代に創られたものだそうです。
不動尊の真下には沢の水に触れられる水場があり、そこに佇むと周囲とは全く違う涼しい風が吹いていました。
二十年前に不動尊を見て、もう一度見たいと思って参加したという地元の参加者の方は、「来られてよかった〜」とため息混じりに大変喜んでいらっしゃいました。皆さま思い思いに写真撮影等を楽しみ、不動尊に見守られながら山道を戻りました。
お昼を30分程過ぎたところで、鏡池に到着!
西岳・本院岳を眺めながらのお弁当タイム。いつもと同じおにぎりも格別においしく感じました


お昼休憩の後は再び、天命稲荷から植物園内の小径を通り抜けてゴールを目指します。
町では猛暑日となったこの日、戸隠でも珍しく汗ばむ陽気となり、うちわを持参していらしたお客さまは大正解!
最後に出会った黄色の「タマガワホトトギス」。
無事、森のまなびや前に戻り、整理体操を行いました。
参加者の方からは「ひとりでは行けない場所なので、参加できてよかった」「ちょうどよい距離と時間だった」など、嬉しいご感想をいただきました。ありがとうございました!
今回のコースはクマさんの棲息地に当たります。行かれる際は単独行動は避け、クマよけの鈴等をご持参ください。
戸隠登山ガイド組合のガイドさんと一緒に歩かれることをお薦めします。 続きを読む
2014年07月24日
戸隠さんぽ隊〜鏡池ソラヨガ〜

こんにちは。梅雨が明け、緑は一層濃くなり、鳥のさえずりも高らかに聴こえてきます。日差しは強いですが、じっとしていて汗ばむということはないので、都会から来られた方には、天国のような戸隠です

今回は、そんな戸隠を象徴する鏡池で7月23日に行った第3回戸隠さんぽ隊・鏡池ソラヨガのレポートです。
子供と一緒に歩ける戸隠のおさんぽコースを歩きながら発掘し、イラストマップをつくるという「戸隠さんぽ隊」の活動もいよいよ大詰め。
今回は、鏡池周辺のおさんぽと併せて、日頃の仕事や子育て疲れを癒していただこうと、ヨガをセットで企画しました。
インストラクターは長野市在住、STUDIO yukey主催の渡辺由紀子さん。
4年前から青空の下で行うヨガ「ソラヨガ」を始め、最近は県内各地でイベントを行うなど、アクティブに活躍されています。
戸隠が大好きで、「鏡池の前でヨガをすると気持ち良いよー」というお話を以前から伺っていたご縁で、今回講師としてお招きしました。
戸隠さんぽ隊のレギュラーメンバー2組(親子)に加え、長野市内外から10名の方が参加。お子守りスタッフ2名と、地元のケーブルテレビのカメラも入り、なかなかの賑わいになりました。
お子さんたちは、いつもと違う状況に、なかなかママから離れませんでしたが、こんな光景もかわいいですね。
青空の下で日光を浴びながら、自然と一体化することが、ソラヨガの醍醐味。
鳥の囀り、虫の羽音、地面の温かさ...そいうったものを感じながら、呼吸に集中することで、心が解き放たれます。
私も、少しの時間でしたが、芝生の上に横になり、太陽を見上げ、大地のエネルギーを全身で感じることができました。
標高1150メートルの鏡池でも夏日となったこの日は、30分もすると、じんわり汗をかき、体のなかの悪いものが解毒されたようで、皆さんスッキリ素敵な表情になりました!
ピカピカになったご一行。お次は戸隠さんぽ隊として、鏡池の周囲の森をぐるりおさんぽです。
若干雲はかかっていましたが、池の畔に立つと、写真を撮らずにはいられません。
鏡池を含む戸隠高原は上信越高原国立公園。国民の共有財産を守るため、ルールは守りましょう。そして、自然動物も生息していますので、一人歩きは禁物。熊鈴、ラジオなどを携帯することが推奨されています。
木漏れ日が差し、野鳥さえずる森の中を進んでいくと、階段があり、わくわくするような雰囲気


木道の上を進んでいくと、ガールたちの心をつかむ撮影スポットがあった様子。雪融け水のせせらぎです。
15分ほど歩いて天命稲荷に到着。
せっかくなので、戸隠森林植物園との境に立つ、女性修験者(?)の像も見ていきましょう。
南北に2体あり、植物園側の方は、少し小首をかしげているようで、癒し系です。

天命稲荷から戻って来たところで、さんぽ隊レギュラーメンバーのおチビさん達と合流。
1歳半のお子様を連れながら、毎回おさんぽに参加してくれた2組のママさん、本当にありがとう!
この先の、もうひとつの撮影スポット、鏡池へ注ぐ小川。
あまりにも素晴らしいロケーションに、橋の上でヨガのポーズをして撮影するガールもいましたよ

ここから5分ほど緩い坂道を登っていくと、ゴールです。
最後は、Studio yukeyオリジナル信州山の日記念「山のポーズ」。今年から、7月の第4日曜(2014年は7/27)が長野県「信州山の日」に制定されました。
皆さん、お疲れさまでした!
続きを読む
2014年07月11日
戸隠夏花図鑑

こんにちは。台風8号が去り、久しぶりに現れた戸隠連峰。緑が一層濃くなったように感じます。
台風の被害に遭われた地域の方々に心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
さて、戸隠スキー場の越水ゲレンデの夏のシンボル・ヤナギランが開花したと聞きつけ、早速見に行って来ました。
ゲレンデの一部(フランススキー学校横)はマレットゴルフ場になっていますが、その傍らから少し登って行くと、「お花畑」のような草原が広がっています。

里でもよく見かけるウツボグザ。ヒョウモンチョウの一種と思われるチョウが盛んに蜜を吸っていました。

夏に花穂は枯れ、「夏枯草(かこそう)」として利尿薬にも使われるそうです。
白い花はカラマツソウ。よく見ると線香花火のような糸状の花です。

ヤマオダマキはこれからが見頃。一輪だけ咲いていました。

足下にスミレより少し大きい、かわいらしい花を発見!

図鑑で調べたところ白山風露(ハクサンフウロ)のようです。いかにも涼しげな名前ですね

5分ほど登って、ようやく本命のヤナギランの群生地に到着。

風が強いにも関わらず、じっと離れようとしないシジミチョウがかわいい


ヤナギランは、まだまだ咲き始め。これから8月上旬頃まで楽しめそうです。
夏の花見頃とともに、夏野菜の旬ももうすぐです!
先日、長野市民新聞でも取り上げられましたが、戸隠の高原野菜の通販「戸隠旬もの便り」がいよいよ今月下旬から販売スタートします。
お百姓さんたちが、手塩にかけて育てた旬の野菜は「紫峰の里 旬野菜セット」として、ご家庭にお届けします。
この「紫峰の里」とは、戸隠高原の別称。
山並みに夕陽が隠れ、夜の静寂が訪れる前の一瞬、高原の周囲の霊峰が紫色に輝くといわれます。
この輝きを受けて育った瑞々しく、滋味深い野菜。
現在、ご予約承り中です!
お中元代わりにお野菜をお届けするというのもいいですね

2014年06月27日
手づくりを楽しむ山の暮らし(2)
こんにちは。夏至を過ぎ、そばの花が満開となり、そろそろ葉タバコの花が咲きそうな戸隠です。今年はマイマイガの幼虫が大量発生し、一部の山では笹の花が咲くなど、自然界では節目の年となっているようです。笹の花は約60年周期で開花し、その後笹薮は枯れ、同じ場所には二度と生えて来ないそうです。山で暮らしていると、自然の恩恵とともに、その不思議や厳しさを肌で感じることができます。
ということで、今回は山の恵み、竹にまつわるお話です。
6月のある土曜日、戸隠地区の南端、裾花川の左岸にある炭焼き釜で、竹炭の炭焼きが行われました。
主催者は裾花川右岸の下祖山地区を中心に活動している「下祖山ホタルの会」羽田静男さん。
竹林の間に、ドラム缶でできた炭焼き釜が2つ。10年程前にホタルの会の活動の一環として、長野市の補助金を得て作ったそうです。
過疎化が進む里山の竹林を活用して竹炭をつくり、できた炭はホタルの水路に入れて水質浄化に役立て、地区のバザーで販売することで地域の活性化にもつながればと、地道な活動を続けていらっしゃいます。
年に何度か炭焼きをするそうですが、毎年6月には淡竹の竹の子採りと竹の子汁もセットで楽しめるということで、私も5歳と2歳の子どもを連れて参加させていただきました。
釜の中に50cmほどに切り揃えた竹を並べ、点火してから約3時間、釜の中の温度を80度に保ちます。温度が安定するまでは扇風機や内輪で扇いで火力を強くする作業が欠かせません。
もくもくとよい調子で煙が上ってくると、竹の子汁づくりも始まりました。
まずは、皮剝き。先端から下に向って包丁で切り込みを入れると、簡単に剥くことができます。
次に食べやすい大きさに切ります。
そして洗って鍋に入れ、1回茹でこぼしてアクを抜き、サバ缶(水煮)とともに煮ます。

仕上げに味噌を融けば出来上がり!簡単ですが、この時季しか食べられない、長野ならではの郷土食です。
お汁が出来上がるまでの時間稼ぎ、というわけではありませんが、この日のもうひとつの目的を果たすため、子供を連れてお散歩へ。
炭焼き釜から数百メートル上がったの山の一角に「シンシュウゾウ化石の発掘の地」があるのです。
「貯水池のところに車を停めて、登っていくとお宮があるから、そこを通り過ぎて登って行くとあるよ」といわれ、
勢いで山に入りましたが、特に目印もないので心細く、下の子は怖がって「だっこして〜」....

林の陰にそれらしいものが見えたときには、大発見をした気分でした

褶曲した地層の中に、「シンシュウゾウ下顎化石 1983.11.6〜12.4発掘」と記されています。
発掘したのは当時戸隠小学校の5年生!こんな山の上で、よく発掘したなぁと、感心するばかりです。
ちなみに、現物は戸隠地質化石博物館に展示されているということで、後日見て来ました。
長野県の天然記念物。300万年前の地層だったと知り、改めて感心!
途中で竹の子など取りながら、再び炭焼き釜まで戻ってくると、ちょうどお昼。
アツアツの竹の子汁をいただきました!味噌汁が苦手で普段はあまり食べないお姉ちゃんが、お代わりをして食べたほど、おいしかったです!
(子ども達は竹の子ではなく、サバの身を喜んで食べていましたが)
竹炭の方はこの後3時間ほど加熱して、消火。
一晩冷まして、翌日、釜の蓋を開けてみると....
黒光りした竹炭が現れました!
羽田さんいわく「竹炭同士を重ねたときに、カラカラと締まった音がすれば、上出来」だそう。今回焼き上がった竹炭はとてもいい音がしましたので大成功ということです。
水洗いして炊飯器に入れて炊くのもよし、布袋に入れてお風呂に入れれば遠赤外線効果。トイレや押し入れの脱臭、除湿効果もある万能選手です。
我が家では竹かごに入れて机の上に置いてみると、とてもいい感じ♪散らかっていた机上を整理したくなり、勢いで掃除をしてスッキリ
 これも竹炭の効果かもしれません!
これも竹炭の効果かもしれません!
2014年06月20日
戸隠旬ウォーク・新緑の池めぐりレポート
こんにちは。梅雨の前半戦はまとまった雨量がない戸隠。お百姓さんたちは空を見上げては畑に出る忙しい時期です。
さて、今回は6月13日(金)に行われた第2回戸隠旬ウォークのレポート。
前日は夜まで荒れ模様で開催も危ぶまれましたが、集まった14名のお客さまが晴れ男・晴れ女のだったのか、無事開催となりました。
本日のガイドは山の庭 タンネの二代目・里野晋吾さん。越水生まれ越水育ち、あるときは料理人、あるときは山岳レスキュー隊員、さわやかな笑顔が印象的なジェントルマンです。
戸隠キャンプ場ウェルカムハウスで顔合わせをし、タンネ特製のお弁当を各自リュックに詰め込み、出発です!
キャンプ場入口南側の駐車場から、念仏池へ。
その昔、高妻山を登った親鸞上人が発見し、「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と念仏を唱えるとこれに応えるように池底の砂が噴き上がり、声を低くすれば勢いが弱まることからその名を付けられたという念仏池。
夏が近づくにつれ藻が増えていきますが、非常に透明度が高く、冷たい湧水です。
「みなさんでジャンプしてみましょう」ということで、里野さんの発声で14名+スタッフ3名がドシーン!
池の底から噴き上がる水に、皆さんから感嘆の声が上がりました。
念仏池を後に、一行は県道36号線に沿って種池を目指します。戸隠牧場を通って山側から入るコースも検討していましたが、前夜の雨で足下が悪いということでコース変更。それにしても雨上がりの緑は、一層鮮やかさを増し、目の保養になります。耳にはエゾハルゼミの声がシャワーのように降り注ぎます。

ゆっくり15分ほど歩いて市町村境界の大橋に到着。ここから先は上水内郡信濃町になります。ここから大橋林道を経由した黒姫山登山道(新道)があります。
さらに3分ほどで黒姫西登山道入口に到着。
足下は多少ぬかるんでいますが、登山道はしっかり刈り払いされていて、歩きやすくなっていました。

この道を通るのは一昨年12月の雪乞い祭りのお水取り以来2回目でしたが、雪も寒さもなく、新緑の山を歩くのは本当に清々しいです♪
15分ほどで種池の畔に到着。里野さんから取水口も出口もないのに枯れない池であり、古来この池の水を汲んで雨乞いの神事が行われて来たことが説明されました。種池の主といわれるのが「一かん龍王」で、戸隠神社奥社参道の入口にこの龍王を祀った祠があります。ちなみに毎年6月中旬の巳の日に種池祭が行われ、種池と奥社の祠で祝詞があげられますが、今年は6月16日に行われました。
皆さんが盛んにレンズを向けているのは....?
モリアオガエルの卵が入っている泡巣でした
 よく見るとかなり高い所の枝にも泡が付いていてビックリ!
よく見るとかなり高い所の枝にも泡が付いていてビックリ!既にオタマジャクシもたくさん泳いでいました。
種池は「生態系の豊かさ」を感じる場所でした。たくさんの動植物が共生しているエネルギーに満ちた池です。
丸っこい葉っぱで白い花が咲くヤブデマリ。
お茶で生菓子をいただく時に使うクロモジの若木。

皆さん思い思いに写真撮影を楽しんだり、水分補給をした後、次なる目的地「古池」へ向います。
笹が繁茂する道ですが、よく見ると、小さな花を咲かせた草があります。

ズダヤクシュ。「喘息薬種」と書き、読んで字の如く種子が喘息に効くことからこの名が付いたそうです。
10分ほど歩くと古池に到着!
穏やかな黒姫山と静かな池を前に、「うわ〜きれいー」、「いいところだねー」と皆さんから感嘆の声が上がりました。
古池は農業用のため池として作られた人口池、この辺りも戸隠高原と同様、鉄分が多く含まれる土壌で、水門付近には赤い錆が見られました。
古池の周囲は木道が整備されていて、気持ちよく歩くことができます。
池の西側にある湿地にはミズバショウの群落がありました。残念ながら木道が傷んでいて奥まで入れませんでしたが、アヤメも群生していて、とても眺めのいいところでした。やはりミズバショウの見頃も戸隠より1週間程遅いそうなので、戸隠で見逃した方はどうぞこちらへ

ジブリ映画に出て来そうな祠。何をお祀りしているのでしょうか?
木道の両脇には多様な花が咲き、お花が好きな参加者の方は、感激して立ち止まってはパシャリ(私もそのひとり)。
ベニバナイチヤクソウの群落。
レンゲツツジ。戸隠では見頃を過ぎましたが、古池では1週間程遅く見頃になるようです。
ユリ科のナルコユリ(中央の1本立っている茎)。7月頃鳴子のような花を咲かせます。

そして、今回のツアーの目玉でもあったミツガシワの群生地。
例年6月中旬が見頃となるミツガシワですが、今年は開花が1週間程早く、白い花は既に落ち、実だけになっていました。残念

落ち葉の中からニョキっと顔を出しているのはギンリョウソウ。葉緑素はなく、根から養分を摂る腐性植物です。
花を楽しみながら古池を一周して戻ってくると、水面を一列になって泳ぐカルガモの親子に遭遇。意外とスピーディーなので写真では撮れませんでしたが、とても癒される光景でした

池の畔の芝生の上でランチタイム♪雨雲の動きが活発で不安定な空模様でしたが、お弁当を広げる頃には運良く青空も出てきました

本日のガイド里野さん自らが作った山菜たっぷりヘルシー弁当!
ウドとシラスのきんぴらに、フキの煮物、メインはノアザミの牛肉巻き。山菜には出汁がよくしみ込んでいて苦みは少なく、とても食べやすく、皆さん「おいしい」といいながら食べていました

静かでゆっくりと時間が流れる古池で、優雅なランチタイムを堪能したところで帰路につきました。
往路も行きと同じ道なのでとても早く感じましたが、足はいい具合に疲れ、普段運動不足の方にとってはよい運動になったようです。
13時半過ぎに戸隠キャンプ場入口に到着。皆さま怪我もなく、楽しんでいただけたようです。
次回は7/25(金)鏡池と不動尊磨崖岩を巡る涼感ウォーキング。戸隠の知られざるパワースポットを訪ねます!
ご興味のある方はぜひお申し込みください。
2014年06月13日
戸隠山のてっぺんで。
こんにちは。梅雨空の下、草木が著しく成長する季節となりました。
梅雨の晴れ間には田畑の雑草を刈る刈り払い機の音が鳴り響く季節でもあります。草や害虫と葛藤しながら、大自然の中に住まわせていただいていることを実感する日々です。
さて、去る6月3日、戸隠地区山岳遭難防止対策協議会で、高妻山・戸隠(表)山・黒姫山・飯縄山・西岳の登山道調査を実施されました。学生時代以来10年のブランクがある私でしたが、観光協会に勤めさせていただいている以上は一度は登っておきたいと、意を決して戸隠山の調査に同行させていただきました。
登山道の詳細等について、初めて登った私がレポートをすることはできませんが、大変心に残る経験だったので、記録として残させていただきたいと思います。

戸隠神社奥社からの急登。一気に400メートルぐらい登ります。

道中にはこんな落とし物もあります。猿の糞。踏むと厄介なので要注意!

五十間長屋で最初の休憩
当日は暑くもなく、寒くもない、まずまずの登山日和でしたが、山頂から見えるという富士山や北アルプスは雲に隠れていました。その分、足元に見える戸隠の森の緑が素晴らしく、蟻の塔渡りから振り返って見えた鏡池のきらめきなどが心に刻まれました。

シラネアオイ。庭で咲くものより、色が濃いようでした。
「木曽路はすべて山の中にある」とは島崎藤村の名言ですが、「戸隠はすべて緑の中にある」ということをつくづく感じました。これだけの緑に包まれた、標高の高い土地に、数百年の歴史ある御師集落があり、農村地帯があり、心やさしい人々が暮らしている戸隠。「天空の城ラピュタ」のように奇跡的な場所だなと、戸隠山のてっぺんで、そんなことを思いました。

百間長屋
修験者が窟に籠もり、いろいろな術を身に付けるべく修行した山であることも、これまでは「遠い昔の話」としか思えませんでしが、実際に登ってみるとその跡を見ることもでき、「生の歴史」を感じることができました。

また、山岳レスキュー隊の皆さんの登山者の安全を守るための地道な活動、プロ意識に触れ、大変勉強になりました。

戸隠スキー場のある瑪瑙山方向。
蟻の塔渡り(山頂方向)
蟻の塔渡り(鏡池方向)
登山道入口からの40分の急登、蟻の塔渡りの断崖絶壁は言うまでもなく、九頭龍山から滑滝までは残雪もあり、大変足元が悪い状態でした。また、不動滝・滑滝は「登山道」というイメージからはほど遠く、「ここ通るの?」と疑いたくなるような沢の上を下ります。
八方睨み
日本百名山 高妻山
八方睨みより少々下ったところにある山頂標識。地味な感じなので危うく通り過ぎそうになりました。
九頭龍山山頂。あいにく視界不良でしたが、ここで昼食休憩。おにぎりを食べている間に額をアブに刺されました。

水墨画を見ているような絶景。
一不動避難小屋。宿泊は禁止。急な雨や雷の際にエスケープすることができます。
残雪残る斜面から不動滝へ。ロープを持っていても危険です。
氷清水。まさに「生き返る」おいしさ!。ペットボトルに入れて家に持り帰り、自宅で飲んでも格別においしかったです。
帯岩。鎖が切れていて、補修しながら進みました。後ろ(下)を見ずにカニ歩きです。
危険な箇所を全てクリアして、迎えてくれた二輪草の群生には本当に癒されました。
登山道入口から約6時間。戸隠牧場に到着!
とはいえ、花や景色を愛でる「トレッキング」を楽しむ山ではありません。
登山を検討している方は、必ず「登山計画書」を提出し、戸隠山をよく知っている人と一緒に登ることをお薦めします。
また、終始頭の回りをアブが飛び交い、油断すると刺されますので虫除け対策(ハッカ油がよく効きます!)をお忘れなく。
2014年05月19日
春の花めぐり越水さんぽ。
山の庭タンネ前庭のカタクリ
こんにちは。飯縄山の雪が消え、芽に若葉、風薫る五月となりました。
山野草や野鳥好きの方には最高のシーズン。ウォーキングイベントも多い時期です。
ということで、今回は5月14日(水)に開催した戸隠さんぽ隊「越水さんぽ」の様子を報告致します。
ちょうど1年前に結成した戸隠さんぽ隊。今年もファミリーでおさんぽできるコースをイラストマップにするため、3回計画で地区内を歩く予定です。
今回は戸隠・飯綱地区にお住まいの3組の親子が集まってくださいました。スタートは戸隠森林植物園駐車場。
幸先良く植物園の駐車場入口の大山桜は満開

意外と知られていませんが、長野県指定「小鳥の森」石碑の奥に仏像(万霊供養の塔)が立っています。

道路を渡り、越水ヶ原へ。ウグイスの鳴き声がさかんに聴こえます。
稚児の塔を通過。
「妻にきた男からの艶文を、字の読めない夫に代わって読んだ養子の子供が、夫婦仲が壊れることを心配してただの手紙のように読んだ」と書いてあります。この塔の意味を子供に説明するのは難しいですね

次に、公明院に立寄り、飯綱権現石像、日本六十六州一の宮、釈長明火定の地の石碑等を見学。戸隠信仰の歴史に思いを馳せた後、境内のカタクリ群生地へ。
木漏れ日差すカタクリの苑。この時期にしか出会えない奇跡のような風景です

かつて越後からの参拝の道であった旧越後道男道を歩きます。
越水ヶ原はスキー場へ向うメイン道路は舗装路なので、おさんぽには旧道がよいかと思って選んだ道ですが...小さなお子さまを連れて歩くのは難しいかなと、ちょっと反省…。そもそもここはかつて女性が通ることのできなかった男道。今も女性一人で歩くのは控えた方が良さそうです(緑が茂ると薄暗いかもしれません)。
一休みできるベンチスポットは要チェック!
「女人結界の碑」を経て、山の庭タンネへ。ここまで大人だけだと30分の道のりを約1時間かけて到着です。満開のカタクリを見ながら休憩。宿のご主人との会話も楽しみました。
シラネアオイも優雅な姿を見せていました。
今日参加してくれたお子さんは皆1歳児。お昼が近づき、眠気もやって来る頃 ...
コース後半全部を歩くのは難しくとも、せっかくの機会なので、もうひと頑張りしてもらうことに。
戸隠山の絶景に励まされて再出発です!
タンネから100メートルほど北へ歩くと、せせらぎの小径の入口があります。
戸隠スキー場の第4駐車場へ至る緩やかな斜面には幅2メートルぐらいの木道が整備されています。
紫色のミヤマスミレが可憐な花を咲かせていました。
10分ほど歩くと、ぼーっと佇むのにちょうどよい木陰が現れ、ベンチも2ヶ所にありました。
一人のお子さんがママの抱っこで寝てしまったので、スキー場第4駐車場からは車移動に。
最終ポイント、白樺荘の水芭蕉園へ。車で3分、歩けば30分弱の道のりです。
妖精のような白い姿と、甘い香り。しばし、現実を忘れて白い妖精と、リュウキンカや二輪草の群生に心を潤しました。
今回は、やむを得ず一部車を使いましたが、予定通り12時前に植物園駐車場へリターン。
イラストマップ化するにあたって、今回のコースは「親子で歩ける」に注釈付となりそうですが、
貴重な体験となりました。参加してくださったママさん達、どうもありがとうございました!
次回は6月18日(水)。大久保〜野鳥の里ペンション村を歩きます。
初めてのご参加も大歓迎です!
2014年05月13日
「戸隠旬ウォーク」レポート
こんにちは。たくさんのお客さまがお見えになったGWが過ぎ、これから1ヶ月ほど、新緑が素晴らしい時期を迎える戸隠です。
観光協会の事務局から見える飯縄山の山裾にも新緑が見えるようになりました。この時期の緑のグラデーションには本当に目が奪われ、心癒される彩りです。
さて、今回は5月8日(金)に行われた「第1回戸隠旬ウォーク〜ミズバショウと野鳥のさえずりを楽しむ春の息吹ウォーキング」にスタッフとして参加しましたので、写真とともにご紹介します。
今年からスタートしたウォーキングイベント。「観光コース」ではなく、旬の草花や知られざる絶景をゆっくり歩きながら楽しんでいただきたいと、戸隠の自然を熟知し、ガイド経験も豊富な戸隠登山ガイド組合のガイドの案内で歩くコース設定。初回にも関わらず、県外の方を含む10名のお客さまにご参加いただきました。
この日のガイドは、民宿鳥見亭のご主人、バードウォッチング歴20年以上の吉井一夫さん。
自称「てるてる坊主」とおっしゃる晴れ男。雲が多めではありますがまずまずのお天気に恵まれました。
戸隠森林植物園森のまなびや前を出発し、手始めはみどりが池に泳いでいた水鳥の説明。「小さいカモなので"コガモ"です!」
バリアフリー木道を奥社方面へ。
園内にはたくさんの鳥の巣箱がかけられていますが、鳥のサイズによって穴の大きさが違っているそう。知らなかった!
木の根本に注目!冬の間に雪に埋まっていた部分がネズミ等に皮を齧られてしまっています。こうなると、木は死んでしまうそうです。恐るべき害チュウ...
吉井さんが双眼鏡で何やら見上げています。
♪ピリピリリ..
「サンショウクイという鳥です。山椒は小粒でピリリと辛いと言う訳です
 」
」素人には鳥の姿こそ見えませんでしたが、その鳥のさえずりとネーミングの妙が心に残りました!
10分程歩いて入口広場へ出ました。
カタクリ、ヤマエンゴサクの共演。
案内板の脇から再び木道を歩きます。右側に水芭蕉の群生が広がり、おとぎ話のような光景が
 参加者の皆さんはカメラをパシャパシャ。
参加者の皆さんはカメラをパシャパシャ。水芭蕉の間をチョンチョンと歩くアカハラにも出会いました(残念ながら写真は撮れず)。
「しばらくここでぼーっとしていたいわ」という声も聞かれましたが、今回はウォーキングなので、どんどん行きます。
近くには二輪草も咲き始めていました。二輪草は風味がよく、味噌汁に入れたりもするそうですが、葉っぱがトリカブトと酷似しているので要注意です

こちらは富貴草(フッキソウ)。名前がおめでたいので、雑草を防ぐため畑や庭に植える人もいるとか。
行者ニンニクも群生。戸隠森林植物園は国立公園なので、採集はできませんが、お好きな方にはたまらないですね。

木道を離れ、小鳥のこみちへ。杉等の常緑樹も混じる林の中です。
スミレサイシン。川端康成の「牧歌」という随筆にも登場する少し大きなスミレ。低地ではあまり見られない貴重な種です。
そして、キクザキイチゲ。ほのかな紫色がとても上品です。
こちらはカンバの仲間の大木。倒れた幹から樹が生え、こんな形になっています。
昔の人が薪をとるため雪上に出ている部分を切り、切り株から新たな芽が出て成長した樹=「アガリコ」も、戸隠の森の中にはたくさん見られます。

一行は外周の小径へ。

針葉樹の森を抜け、明るくなった林の上で耳を澄ませると「フィーチーチー」という声。
声の主はクロジ。「アカジではないですよ。アオジという鳥はいますが、鳥にアカジはないんです」と吉井さんの明解説が入ります。
ミズバショウの群生地でもあり、ツキノワグマの餌場でもある植物園。クマの通った笹薮やイノシシが土を掘り起こした跡など、野生を感じる道を10分ほど歩きますと、パッと視界が開け、こんな景色が。正体不明の女人の像(向かい合って2体あります)。
小川に架かる橋を渡ると小さなお社が現れました。
天命稲荷です。戸隠最後の修験者と言われる姫野光明師が建立し、伊勢の下宮の御祭神・豊受大神を祀っています。
一節によると、戦国時代にこの地は首塚であり、その生霊を鎮めるためにお社を建てたとか...。
せせらぎに沿って5分程歩くと鏡池が見えて来ました。
鏡池前に到着!戸隠連峰の西岳がくっきり見えて、大山桜も見頃。素晴らしい景色に皆さんから歓声が上がりました

ここまで終始平坦な道をゆっくり歩いて1時間15分程。皆さま思い思いに写真を撮ったり、15分の休憩を楽しみました。
帰りは天命稲荷から東へ向う林道を歩きました。
冷たい風が吹き始め、雲行きが怪しくなって来ました。ミズバショウが咲く林の向こうに戸隠山が見える場所を発見!
若干の上り坂で、笹薮が続く単調と思われる道にも、吉井さんの絶妙のガイドが。
戸隠の伝統工芸竹細工に使われるチシマザサ。棹が弓上に曲がっていることから戸隠では「根曲がり竹」と呼ばれ、竹細工の貴重な材料となるため、採取は禁じられています。
一方こちらはクマザサ。熊ではなく隈笹で、冬になると葉が隈取りされたようになります。葉の裏に毛が生えています。
高台園地の下の小高い丘に到着、ゴジュウカラやキビタキのさえずりをききながら、みどりが池まで下っていきました。
ミズバショウとリュウキンカが池をきれいに彩っていました。
集合場所の八十二森のまなびや前に到着したところでぽつぽつと雨が降って来ました。
奇跡的なタイミング。これも「てるてる坊主」の吉井さんのお力でしょうか


参加者の皆さんからは「ミズバショウがこんなに綺麗だとは知らなかった」
「また次回も参加したい」等嬉しい感想をいただき、何よりも無事開催できたことにほっと安堵して解散しました。
次回は6月13日(金)ミツガシワの群生と出会う池めぐりウォークです。
多勢の皆さまのご参加お待ちしております!
2014年04月30日
戸隠が大山桜の名所に!?
こんにちは。いよいよゴールデンウィークに突入ですね。皆さまいかがお過ごしでしょうか?
標高1200mの戸隠高原ではミズバショウの花がまもなく見頃を迎え、これから二輪草にカタクリ、そして新緑が楽しめる、最高のシーズンです。
戸隠牧場のオオヤマザクラの古木の見頃は5月中旬頃(写真は昨年のもの)。開花が楽しみですね


先日、4月19日にはこのオオヤマザクラの実生を種木として植樹するイベントがありました。
一昨年から始まった「戸隠大山桜プロジェクト実行委員会」による5ヶ年計画で、戸隠高原を大山桜の名所に育てようと
5年間で500本の植樹を行う計画です!1本1万円でオーナーを募集し、毎年春と秋に植樹を実施します。
お手植えできない方は委託していただき、記念のネームプレートをかけさせていただきます。
実行委員長はご存知、山の庭タンネの里野龍平さん(写真左の青い作業服の方)。
この日は里野さんが育てた6〜7年目の若木25本を、県内外からの参加者15名程でお手植えしました。
7年目ぐらいの桜は、個体差はあるものの、ちょうど花を咲かせるホルモンが整う頃で、来シーズンは花が咲くだろうとのことです。
下界は上天気でしたが、標高1300m近い戸隠牧場は、厚い雲に覆われ、吹く風に手がかじかむような寒さ

それでも、皆さん思い思いにお手植えを楽しんでいる姿が印象的でした。
生まれ育った戸隠の地に何かを残したいという年季の入ったご夫婦、戸隠が大好きというご家族、戸隠ファンのグループの30周年に因んで3本植えるというパーティ、愛娘の誕生記念にと、生後6ケ月の赤ちゃんを連れて来てくれた一家...


ネームプレートをかけて、記念撮影

皆さまお疲れさまでした!
この木が大きくなる頃には子供たちも大人になって、私たちはもういないかもしれません。
戸隠高原の自然がそのままに残され、桜の名所となって更に多くのお客さまに癒しをもたらしてくれますように。
夢とロマンあふれる大山桜プロジェクト、皆さまの応援、よろしくお願い致します!
戸隠キャンプ場は明日5/1〜オープン。戸隠牧場にはもう少し温かくなった6月中旬頃動物達がやって来ます。
こちらもお楽しみに!
2014年03月10日
「雪上戸隠参拝ウォーク」レポート(後編)
戸隠は今日も氷点下。朝から季節を間違えたかのような雪がしんしんと降っています。2月の大雪で、もう雪はうんざりという方もいるかもしれませんが、戸隠の冬に雪はつきもの。「雪上戸隠参拝ウォーク」の後半戦、どうぞお付き合いください。
越水ゲレンデを出発し、奥社の杜、戸隠森林植物園を通過し、鏡池入口のそばの実に到着した一行。
おいしい戸隠そばで腹ごしらえをした後、小鳥が池のある雑木林を経由して戸隠神社中社を目指します。
枝の間に熊棚(クマの餌場)がある木。幹にはクマの5本の爪痕が残っていました。上信越高原国立公園内にある戸隠高原はツキノワグマの生息地。こういう光景は珍しくありません。
スノーシューをいったん脱いで県道を渡り、戸隠神社中社へ参拝。このツアーの名称は「参拝ウォーク」なので、神社を外すことはできません!
手水舎の前で神職のガイドから手水の作法の講習を受け、冷たい清水で清めてから本殿へ。
中社の神様は天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)。天の岩戸にお入りになった天照大神様にお出ましいただく方法を考えられた知恵の神様です。今年も受験生が多数訪れたことでしょう。

さて、ここから先は、観光客はもちろん、地元の人も滅多に歩いたことのない空間。中社青龍殿の後方から中社の杜へお邪魔しました。
目指すのは戸隠スキー場中社ゲレンデ。比較的空いているので、静かにスキーやスノーボードを楽しみたい方に人気です。

今回のツアーの目玉として、スキーやスノーボードを履かない方にも戸隠スキー場からの絶景を楽しんでいただけるように、特別にスノーシューを持ってのリフト搭乗が計画されました。が....あいにく、太陽は分厚い雲に覆われ、冷たい北風が吹き始めました。
中社第一ペアリフトでゲレンデを上ると、こんな景色。
晴れていれば戸隠連峰はもちろん、北アルプスや遠くに富士山まで見渡すことができる場所ですが、今日は残念。左側にうっすらと見えているのは鬼女紅葉が隠れたという荒倉山塊です。

瑪瑙山を前方に眺めながら、緩傾斜のゲレンデを歩いてゆくと、中社第2リフトに到着。リフトの係員は男前のお兄さんでしたよ

晴れていればこのリフトからの眺めも最高ということですが、残念ながら...

標高1549m、怪無山の山頂に到着!ここで再び、スノーシューを履いたご一行。林の中を下ってゴールのゲストハウス岩戸を目指します。
曇天の中ですが、大学のスキー部など多勢のお客さまが滑りを楽しんでいる中の移動。晴れていれば、こんな景色が見られたことでしょう。

さて、この後、ドリームコースと岩戸コースの間の林を下ったのですが...ゴメンナサイ!ショートカットを狙って急斜面を降りたら、新雪に足を取られ、撮影をする余裕がありませんでした
 カメラの操作に手袋の着脱を繰り返していたら手がかじかんでしまったのも事実
カメラの操作に手袋の着脱を繰り返していたら手がかじかんでしまったのも事実
今回の取材では一眼レフとiPhoneを持参していましたが、iPhoneは気温が低すぎると(おそらく零下)電源が落ちてしまうということがわかりました(一眼レフもシャッター関係が不調になりました)。貼るカイロで温めてどうにか復活しましたが、次回は、もっと操作しやすいコンパクトカメラを持参したいと思います。
そんな反省を胸に、無事下山。すると、雲に隠れたはずの戸隠連峰が出迎えてくれました!

ガイドさん情報により、望遠レンズで除いてみると奥社参道杉並木や、奥社本殿の一部が見え、また感動

午後4時。予定時間を若干遅れてゲストハウス岩戸前に無事全員が到着し、お開きとなりました。
今回、スキー場開場50周年を記念して特別につくられたコース。実際歩いてみるとかなりハードな行程で、腰から下がだるい感じでしたが、参加者の方からは、「よい運動になった」とか、「普段は歩けない場所を歩けて楽しかった」とうれしい感想が聞こえました。
ゲレンデにはまだまだ新雪が降り、例年の3月とは思えないほどの雪質が維持されています。
残りわずかとなりましたが、まだまだ遅くありません!スキーヤー、スノーボーダーの皆さま、戸隠スキー場にて魔法の粉雪と絶景をお楽しみください!
2014年03月10日
「雪上戸隠参拝ウォーク」レポート(前編)

こんにちは。啓蟄を過ぎてもまだ気を抜けない寒さが続く戸隠です。
大人はもう雪は嫌だなんて弱音を吐きますが、子供たちは新雪が降れば大喜びで遊んでいます。
さて、今回はそんな子供心忘れない大人のための雪遊びイベント、戸隠スキー場開場50周年を記念して3月7日(金)に行われた「雪上戸隠参拝ウォーク」に参加して参りましたので、写真とともにご報告します!
この日は前日までの雪も上がり、青空も見えるまずますのお天気に恵まれました。
集合は戸隠スキー場越水ゲレンデのゲストハウス岩戸。
出発前にレンタルスノーシューをフィッティング。スノーシューは長靴やスノーブーツに装着できる西洋かんじき。初めてでもコツを覚えればすぐに装着でき、新雪の上を歩くことができます。今回は新雪が降った後なので、ブーツやパンツの丈が短めの方は雪が入ってしまわないようにスパッツを付けていただきました。

戸隠地区外から6名(1名は東京から!)、地区内から4名、計10名の参加者とスタッフ6名が加わり、賑やかにスタートです。
スキー場の第5駐車場からの眺め。戸隠連峰はこの後、雲に隠れてしまいそうなので、初めに目に焼き付けておきましょう。
まずはスキー場からほど近い越水ヶ原の雪原で足慣らし。ミズナラやシラカバの雑木林が広がります。

今回のガイドは、鳥や植物に詳しい人、戸隠神社の神職、そば打ち職人と、個性的な面々。道中には豆知識がいっぱい、参加者を飽きさせません!
豆知識その①
雑木林の木々をよく見ると、ツル植物が絡まっている木がけっこうたくさんあります。こちらはイワガラミ。つるアジサイに似た花を咲かせます。
豆知識その②
テンの足跡。エサを求めて雪原を走り抜けた跡がくっきり。
豆知識その③
ツルマサキ。こちらは珍しい常緑のツル植物です。
県道36号線を横断し、戸隠神社奥社の社へ。大鳥居が見えると喜びの声を上げる人も。

ご存知、奥社参道は立春・立冬の際に太陽が正中線(参道の真ん中)を通るように設計されています。
立冬から冬至までは太陽のない、死の世界。冬至から立春にかけて徐々に生命体が活動を初め、立春に生命体が甦るという「生命復活」のストーリーを踏んだ設計はこの場所の神聖さを際立たせます。
奥社へ向って左側は湿地、右側は乾燥した雑木林でたくさんの巨木が存在します。
ということで、右側の森へ進路を進めます。
専門家も賞賛するというダケカンバの大木。
こちらもダケカンバ。その色艶の良さから「戸隠のヴィーナス」と呼ばれているとか!?
触っておけばご利益あるかな

奥社の杜を30分ほど歩いた頃、現れたのはご存知、ミズナラの巨木「王様の木」

王様の前で、しばしティーブレイク。周囲には高木がなく、広場のようになっています。夏には根曲がり竹が繁茂する薮になり、王様全体を見ることができないということで、ますますこの奇跡的な出会いに感動!
参加者の皆さんも、思い思いに写真を撮ったり、お菓子で疲れを癒しました。
王様とお別れしてから10分ほど歩くと、奥社参道に合流。随神門に到着です。
冬期は雪崩の危険があり、本殿まで行くことはできないので、杉並木の前で奥社と九頭龍社を遥拝。
全員で記念撮影をしました。

時刻は既に正午を回り、お腹も空いて来た頃。この後、戸隠森林植物園内を急ぎ足で、通り抜けることに(撮影も省略しました
 )
)雪の下に隠れた水芭蕉の小径を通り、高台苑地を登り下り、みどりが池を通り過ぎ,,,ラッセルがない新雪の上を歩けば太ももが鍛えられ、シェイプアップ効果もありそうです!
雪上をひたすら歩くこと小一時間。ついに昼食会場のそばの実へ到着!スノーシューを脱いだときにはスキー靴を脱いだときと同じような解放感がありました


長時間歩き、体がポカポカになった私は、迷わず冷たいおそばを注文!

瑞々しく、コシがあって美味
 天麩羅もサクサクでおいしく、最高の腹ごしらえができました!
天麩羅もサクサクでおいしく、最高の腹ごしらえができました!一般的なスノーシューウォークならお昼を食べて解散...の場合が多いですが、今回は戸隠スキー場50周年スペシャル!
ということで、この後、意外な展開が....

「雪上戸隠参拝ウォーク 後編」へ続く。
2013年11月15日
神無月の雪見ツアー

こんにちは。2週間ぶりの更新になりました。この間、季節は秋から冬に早変わり。
お客さまのお問合せも、「路面の雪の状況は?」が最も多くなりました。
さて、11月12・13日と、この時期にしては珍しく、まとまった積雪があった戸隠地区。ちなみにこの日、旧暦では神無月(10月)の10日にあたり、出雲大社に全国の八百万の神々が集う日とされています。戸隠神社の大神様の不在に、冬将軍がいたずらしに来たのかもしれませんね!?
スキー場開きは1ヶ月後ですが、ウィンターシーズンを先取りしたような雪景色を、撮影して参りましたのでご覧ください!
トップ写真は、よく撮影スポットにさせていただいている豊岡地区(標高900m)。この辺り、路面の雪はほとんど融けています。
続いて標高1000m。宝光社地区入口のしめ縄の下に雪が!氷柱の上に雪がつもったようです。

宝光社から鏡池へ向う道。既に除雪はされていましたが、カラマツの落葉があり、路肩に雪もあるので、冬用タイヤが必要です。

鏡池(標高1150m)に到着。

池の周りはすっぽりと雪に包まれています(雪かきはされていません)。今日の雨でだいぶ融けたとは思いますが、革靴やスニーカーでは滑りますのでどうぞお気をつけ下さい。

快晴、無風。池の上は一部凍結している場所もありましたが、よい写真が撮れました!
鏡池から奥社方面へ。

日陰は路面にも雪が残っていますので、慎重に。
標高1215m。奥社前駐車場。

ツアーバスのお客さまもいらっしゃいましたが、参道には雪があり、本殿(1350m)はとても寒いので、身支度をしっかりしてお出かけください。
もちろん、戸隠そば祭り「半ざる食べ歩き」も好評開催中です。

農産物直売所では秋の味覚もまだまだ豊富に揃っています!



野菜直売所は11月24日まで毎日営業。
戸隠そば祭りも同日までです。
冬の入口の戸隠高原へ、どうぞ暖かくしてお出かけください。

撮影協力:手打そば処千成、戸隠高原野菜組合野菜直売センター
2013年09月11日
戸隠花図鑑(4)
こんにちは。
農家の高齢化が進み、あちこちの休耕田がそば畑に衣替えしている戸隠ですが、
地形をうまく利用した田んぼに稲穂が垂れる風景は、やはり、何度見ても素晴らしく、
この風景がいつまでも残ってほしいと勝手に願う秋の空です。
さて、今回は、秋の花特集第2弾!
戸隠森林植物園や越水ヶ原(戸隠スキー場近く)で8月末から9月初めにかけて撮影した花や木の実をご紹介します。
トップバッターは清楚な印象のアケボノソウ(リンドウ科)。撮影地:戸隠森林植物園(以下同)

花びらの先の斑点を明け方の星空に見立てて和名が付けられたそう。ロマンチック

こちらは、珍しいアケボノシュスラン(ラン科)。

ツタの先に花を咲かせるツルニンジン(キキョウ科)。
長野県花といえば、リンドウ(リンドウ科)。撮影地:越水(以下同)

見上げれば、樹々にも実りの秋が。
ヤマボウシ(ヤマボウシ科)。
風に揺れるとかわいいツリバナ。
秋そばの花は、見頃満開を迎えております。お早めにお出かけください!
2013年08月21日
戸隠花図鑑(3)
こんにちは。例年、お盆が過ぎると一気に涼しくなる戸隠ですが、
残暑が厳しい今年も、朝晩はぐっと涼しく秋の気配が感じられるようになりました。
(写真は県道76号線豊岡地区の秋そばの花)
この「とがくし便り」を初めてからおかげさまで1年が経ちました。
四季を通じて戸隠の魅力が発信できているか、
戸隠ファンの皆さまが求めている情報は何か、
猛進するだけでなく、立ち止まりつつ、前進していきたいと思います。
ということで、ゆっくりと自然観察や撮影をするにはもってこいの季節、
今回は戸隠森林植物園内で見られる晩夏〜初秋の野の花をご紹介します。
トップバッターはこちら。
高原に秋の訪れを伝えるマツムシソウ(松虫草:マツムシソウ科)。
柚の香りがするというユウガギク(柚香菊:キク科)。
〜黄色シリーズ〜
キツリフネ(黄釣船:ツリフネソウ科)。
ハンゴンソウ(反魂草:キク科)。
キンミズヒキ(金水引:バラ科)。
ケナシヤブデマリの実(薮手鞠:スイカズラ科)
※花は戸隠花図鑑(2)に掲載。
最後は、戸隠神社奥社参道の妖精。
オオシラヒゲソウ(大白鬚草:ユキノシタ科)。花だけでなく、輪っかのような葉の造形美も見事です。
秋そばは五分〜七部咲きとなっている畑もありますが、戸隠地区全体としては9月上旬からが見頃となりそうです。
秋風吹く高原へ、ぜひお出かけください。
2013年07月25日
戸隠で夏休み。〜戸隠キャンプ場&牧場へ〜
こんにちは。
今週は雨が降ったり止んだり、普段以上にマイナスイオン多めの戸隠です。
さて、学校はいよいよ夏休み。ご家族でお出かけになる機会も多いと思います。
私の子どもの時代を振り返ると、夏休みといえばプール、花火、そしてキャンプ。
キャンプで何を作るかを考え、買い出しに行くのがとても楽しみでした。
そんなことを思い出しながら、よく晴れた土曜日の朝、子どもを連れて戸隠牧場&キャンプ場へ出かけました。
昨年リニューアルオープンした戸隠キャンプ場。
県道36号線の戸隠キャンプ場バス停からすぐの所にキャンプ場の受付を兼ねた戸隠高原ウェルカムハウスがあります(詳細は記事の後半で)。
この日は隣接の牧場へ直行。
キャンプ場入口から700m先の牧場管理事務所前の駐車場が利用できます。
牧場の入場料は小学生以上200円。
五地蔵山と高妻山を正面に見ながら、セミとカッコウの声をBGMに100mほど歩きますと動物たちが見えてきます。
牧場内は愛犬を連れてのお散歩もOK(リードを付けて)。
ドッグラン(無料)もあるので、ワンちゃんの運動にも最高の環境です!
まずはウサギ、ミニブタ、ヤギ、子牛などと触れ合える「ふれあい動物園」へ。
1歳半の息子は、金網越しに動く動物を見た時点で抱っこを求め、
中に入るとギャン泣き…
 (この後も、ずっと抱っこでした)
(この後も、ずっと抱っこでした)手作りの顔ハメは雨よけガードまで付いていていい感じ!
やや高い位置に穴があるので、5歳の娘はよじ上っていました。
(子ども用に台があるといいですね…。)
ヤギを見ると『3匹のヤギのガラガラドン』を思い出しますが、
ヤギドンたちは本当に草を食べるのが大好き。干し草より生葉が好きなようです。
子牛も近寄って来て、子ども達は大騒ぎ。
牛さん達はみな牛舎でまったりしていましたが、夏休み中は乳搾り体験もできるそうです(1人600円)。※日時等はHPでご確認ください。
ちょうどお馬さんのお昼タイム。おっかなびっくり草を差し伸べる娘。
息子は馬の鼻息で怖じ気づき、またギャン泣き。

遊具や水遊びができるせせらぎもあります。
水の冷たさにびっくり!戸隠連峰の雪融け水です。

新しいトイレにはベビーチェアやウォッシュレットもあり、清潔で快適です。
順番が逆になってしまいましたが、牧場からの帰り道、ウェルカムハウスへ立寄りました。
外には野菜の直売コーナーも。バーベキューに使えそうですね!
まずは娘とお約束のソフトクリーム(バニラ・チョコミックス)をいただきます。
牛乳の味が濃厚なわりに、さっぱりしていておいし~!
※通常価格350円ですが、戸隠観光案内所にあるクーポン券を使えば100円引きになります。(夏期限定)
ショップ内で目を引いたのは「となたな」というコーナー。
「と」がくしと「な」がの逸品が並ぶ棚&店ということで、リンゴジュースからお醤油までキャンプ場スタッフ一押しの特産品を集めたそう。お土産に喜ばれそうなものがいっぱいです。

そして、戸隠ならではといえば、登山記念のピンバッジ(530円)。

戸隠山と高妻山をつなげると戸隠連峰が出来上がります!
こちらは戸隠Tシャツ(S~L 2500円)。
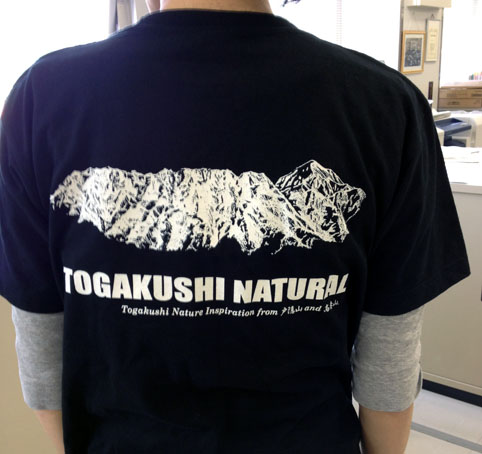

いずれもスキーハーフパイプの日本代表選手、戸隠出身の曽根原功さんのデザインだそうです。
戸隠散策に必携、熊よけの鈴。金色に光るのは燕三条の真鍮製で一生ものです(2400円)!

戸隠・長野、近隣エリアの観光パンフレットなど観光情報も充実のウェルカムハウス。
今後は戸隠そば店などの紹介もする予定だそうです。
ウェルカムハウス横のトイレも、広くて清潔。
バリアフリートイレにはオムツ替えスペースもあるので赤ちゃん連れの方も安心です!
戸隠キャンプ場には手ぶらでキャンプやバーベキューができるセットもあります。
夏の思い出づくりに、ぜひご家族やお仲間でお出かけください!





